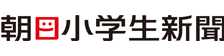
- 毎日発行/8ページ
- 月ぎめ1,769円(税込み)
2017年7月31日付
キャベツを食べさせたウニ「キャベツウニ」を、神奈川県水産技術センター(三浦市)が育てています。磯の海藻を食べつくす「やっかいもの」のウニを残りものの野菜でおいしくする、ユニークな養殖の研究です。飲食店も興味を示し始めました。(猪野元健)
6月末、「キャベツウニ」の初の試食会がありました。黄色い身がつまった400個が地元の農業や漁業、飲食店の関係者ら約100人にふるまわれました。
「くさみがない」「くだもののようにあまい」と好評で、回転ずし店などを経営する会社の川股竜二さんは「さっぱりとしておいしかった。量が安定すれば、すしに使ってみたい。地域の活性化にもなる」と話しました。
水産技術センターが野菜を使ったウニの養殖を始めたのは2年前。ねらいは二つあります。
一つは、漁業者を悩ませていたウニの活用です。10年ほど前から近くの海で海藻が食べつくされる「磯焼け」がおき、海藻をえさにするアワビやサザエも減りました。原因の一つが、今回の実験で使われているムラサキウニです。センターによると、地球温暖化による水温の上昇で神奈川の海でもすみやすくなりました。ムラサキウニは駆除の対象で、身が少ないため食用には向きません。
もう一つは、地元でとれた野菜の残りものの活用です。キャベツなどの生産が盛んな三浦市の農業協同組合によると、傷んだ野菜は捨てることがあるそうです。
「ウニってなんでも食べるよ」。水産技術センターの研究員、臼井一茂さんは職場の先輩から聞いた話をヒントに、ウニに野菜を食べさせてみようと考えました。海にはない植物なので、まずは「食べられるものだと認識してもらうことが大切」。ウニを水槽に入れて約2週間後、おなかがかなり減った状況で野菜をやりました。すると、とげに野菜をからめながら、時間をかけて口に運んでいきました。
「200匹のウニが3個のキャベツを3日で完食。ブロッコリーや大根も食べた」と臼井さん。
成長したウニの身は、食用に広く流通しているキタムラサキウニと同じような成分で、磯焼けした海のウニより身も増えていました。今年から地元の県立海洋科学高校などと協力して技術の確立を目指しています。
「えさが身の味に影響するのかを調べるために、ブロッコリーを食べさせたウニの成分と比べたい。早く口元に運んで食べるようにえさの形も工夫していきたいです」
磯焼けは各地で問題になっています。「キャベツウニ」の養殖技術を広めることで、海藻が回復して漁業の応援にもつながるかもしれません。
沖縄県糸満市の県立沖縄水産高校では、数が減っている食用のシラヒゲウニの養殖に挑戦しています。
海藻の用意は難しいため、えさに選んだのはバナナの葉など「捨てられている植物」で、味や生育状況を調べています。担当の中村信行先生は、「数年後に商品として販売できるようになれば」と話します。


記事の一部は朝日新聞社の提供です。